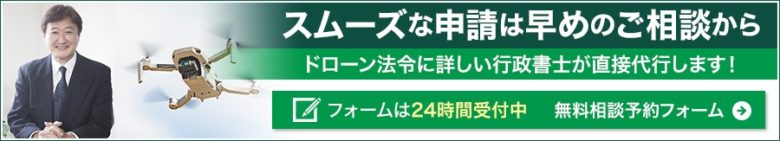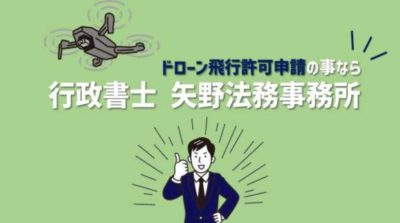
ホームページ掲載機は申請時の写真等、省略可能
ホームページ掲載機リストにある「確認した飛行形態の区分」という欄を見ると
A からG までアルファベットが記載されています。
内容をよく理解しないと違反に直結するケースがあるのできっちりと解説します。
このページで分かること
区分Aで省略できる資料
飛行許可申請には、飛ばす機体の「基本的機能および性能の部分についての資料」の提出が求められ、機体の多方面からの写真と諸元、スペックの資料が必要となります。
しかし、国土交通省ホームページのリストに掲載されている機体で【確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)】の欄に「A」と記されている機体は、これらの「機体の多方面からの写真と諸元、スペックの資料」が省略できるというものです。
逆に、この国交省のホームページのリストにない機体については、機体の多方面からの写真と諸元、スペックの資料を添付する必要があるということです。
DJI機は全てA
“この機種の内容については国交省で既に完全に認められているので飛行許可申請するときにわざわざ出さなくていいですよ”
ということを申請者に伝えているのです。
そうでなければ通常は下のように、前横後ろ方面やプロポの写真、メーカーのホームページなど説明書に載っている基本的な生のスペック部分の写真やスクリーンショット、PDFなどを添付する必要があり、かなり面倒な作業となります。



リストには、資料の一部を省略できる機体について一つずつ具体的に省略できる資料が細かく記載されて出ています。
下の画像が「資料の一部を省略できる無人航空機」のリストです。
このAが書いてあるものは、本来は資料提出が必要となる「基本的機能及び性能」に関する資料が全て不要となるので、その負担がなくなる分だけ申請者側には作業がとても楽になります。
このホームページ掲載機リストの機種にはほぼすべてにAが付いているので、飛ばしたいドローンがこのリストに載っていれば基本的な性能についての資料提出は省略できる…と思っていれば OK です。
DJI機は全てAと書いてあるので基本的な資料は全部不要です。

区分Bで省略できる資料
Bは「新入表面等の上空、地表から150メートル以上の高さの空域の基準」と書いてあり、これだけでは非常に判りにくいのですが、この意味は
空港の周辺か150メートル以上の高さで飛ばすときに必要となる条件をクリアしていることを証明する写真等の資料は不要
というものです。

本来であれば、有人の航空機から見えやすいようにドローンに色を塗ったり蛍光色あるものを取りを付けたり、LEDライトを付けたり等々の基準が多々あるのですが、この「B」と書いてあるものについてはその資料の省略が可能ということです。
区分Cで省略できる資料
Cは、「人又は家屋の密集している地域の上空における飛行、地上又は水上の人又は物件との間に所定の距離を保てない飛行、多数の者が集結する催し場所の上空における飛行のための基準(第三者の上空で無人航空機を飛行させない場合)」と定義されています。
これは、
人又は家屋の密集している地域(人口集中地区DID のこと)や第三者・第三者物件から30m の距離を確保できない飛行をする際に必要となる、プロペラのガード等の安全措置についての写真の添付が省略できる
ということを意味しています。
ただし、これはメーカーが指定しているガードを使っている場合に限られ、そうでないものについては写真の添付や改造の申請が必要となります。

少し自分好みに変えたりすると、さほど飛行に影響ないにもかかわらず改造申請までもが必要になってしまいますので、あくまでメーカーが指定のものに限って資料が省略できるということに注意してください。
プロポを変えた場合も同様です。
区分Ðで省略できる資料
Dは「夜間のための基準」とだけ記されてありますが、夜間飛行では飛行中のドローンが見やすいようにライトが付いていなければならないという基準があります。

ライト点灯した状態で写真撮影をしてそれを添付する必要があるのですが、このDと付記された機体であればそれを省略できます。
区分Eで省略できる資料
Eは「目視外飛行(補助者あり)の基準」となっており、以下とされています。
カメラがついていて手元のプロポのモニターでそのカメラとつながっていることが確認できることや、google マップのような地図が画面の中に写っていて画面の中でドローンの位置がわかること、そして電波の状況などドローンの状態がモニター上でわかることが必要


そして通常ですとモニターのスクリーンショット写真などを添付することとなっているのですが、リスト上の機体が区分「E」となっていれば写真の添付が省略できます。
見過ごせない「E」の注意点
しかし、このEだけは見過ごすことができない注意点があります。
このEのほぼ全てにある「注2」という記載です。

注2についての記述を見ると
下記のメーカー指定の自動操縦システム及び機外の様子を監視できるカメラを装備した場合に限る
と書かれています。
つまり資料を省略できる場合というのは、自動操縦システム(具体的には自動操縦のアプリを装備して使う場合)に限るという意味です。
ということは、自動操縦以外ならば資料の省略はできないということです。
モニターでの目視外飛行は自動操縦でない
では、非常にポピュラーな、プロポのモニターを見ながらの飛行やゴーグルをつけての飛行は自動操縦と言えるでしょうか?
違います。自動操縦ではありません。
普通に手元でプロポなどのモニターを見ながらの目視外飛行や、ゴーグルをつけての目視外飛行をする場合は自動操縦には当たらないということです。
となれば、この場合は資料省略はできません。
ところが多くの方は、資料が省略できる方が断然に楽なので、自動操縦をしないにもかかわらずDIPSに出てくる「自動操縦システムを使用する」…という選択ボタンを選んで許可承認取得しているのが実態です。
許可された飛行法と異なる飛行
DIPSで自動操縦の選択肢を選ぶと、一般的な目視外飛行の空撮でやるようなモニターを見ながらの飛ばし方ができない内容の許可承認になっている・・・にもかかわらず・・・にです。
この点は許可証を見ただけでは判りませんが、ひとたび事故が起きてしまえば「自動操縦じゃないじゃないか!申請内容と違う!」と当局から厳しく追及されることになります。
矢野事務所もここを注意して、実態とそぐわない申請や明らかに空撮したいと言っている場合などは「自動操縦システムを使う」選択はしないようにしています。
これは飛行許可申請の中でもかなり注意しなければならないところです。
目視外の飛行の申請ではかなり注意です。
本来は写真提出
従って、現実と合った飛行をするのであれば、カメラとそのプロポの映像がつながっている写真と、画面の中で機体の位置とか電波バッテリー の状況などがわかるスクリーンショット写真を、省略せずに全部提出して申請することが必要になります。


残念ながら多くの方ほとんどの方はそれができていない。
知らないですし気づいてもいません。
オンラインシステム上は自動操縦システムを使うという選択肢を選べば資料を省略できるので、皆さんそれを知らずにやっているのです。
楽だから…だけの理由です。
何かあった時に100%追及されるところなのにです。
これまで事故がたまたまなかっただけのことに過ぎません。
【注1】に注意
因みに「C」のDID地区等飛行の条件としてある【注1】は、「プロペラガードを装備した場合に限って省略できる」ということになっています。

ということはプロペラガードを装備していない場合はこの資料の省略ができないということになります。
こちらも実際は付けていなくても付けていることにして、資料の省略を受けることができます。
これも「E」と同様にあってはならない当座しのぎの抜け道です。
区分FとGで省略できる資料
次に F の危険物の輸送。それにGの物件投下の基準。
これらFやGが付記されているのはほとんど農薬散布の機体です。
具体的には機種 mg 1と呼ばれている農薬散布用途の機体には F とGが付いています。
Fは「機体について危険物の輸送に適した装備が備えられていること」を、Gは「機体について不用意に物件を投下する機構ではないこと」を証明する写真や設計図等の提出が省略されます。
省略できない場合
ホームページ掲載リストには、省略できる資料とは何なのかについて以下が記されており次の三つとなっています。
①機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
②運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
③追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く)
従って、リストに掲載されていない機体の場合や、区分「A~」に該当しない場合は、これらの資料の提出が求められます。
①に、設計図…とありますが、資料省略できずに申請する場合は写真を添付すれば大丈夫です。
②の「運用限界および飛行させる方法が記載された説明書の写し」とはスペック資料を出せば大丈夫です。
③の「追加装備を記載した資料」については、カメラなどによっては何パターンか切り替えられたりできる機体がありますが、そういったものを何に使うのかということを本来は全パターンの資料を提出しなければなりません。
ただし、この③もリストの欄外に掲載されている機体の対応カメラやアプリについては、その資料は不要ということになります。
令和7年12月で受付終了
以上のように、この機体リストは許可申請するときに結構大事な資料データになります。
以下がそれです。
しかし、国交省HPには、このリンクの下に次のような記述があります。
※上記資料に掲載する無人航空機に係る申請において書類の一部を省略可能とする運用は令和7年12月に終了します
新たに発足した機体認証・型式認証の制度との兼ね合いから来た受付停止措置ですが、今後、飛行許可申請する際の機体関連の資料提出がどのようなものになっていくのかは、はっきりしていません。
ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】
行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。