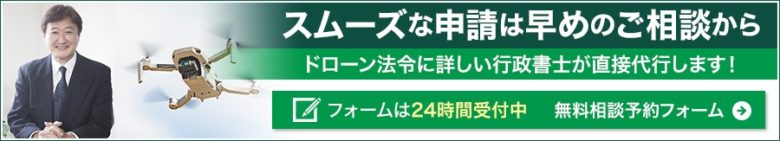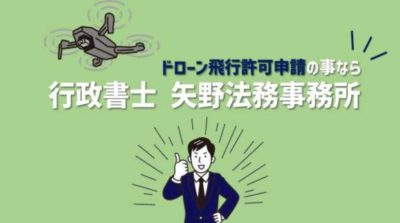
ドローン版車検制度の発足
機体登録をしていない限り屋外で飛ばすことは禁止されます。
1㎝浮かせた時点だけでも違反となり
1年以下の 懲役または50万円以下の罰金の可能性があります。
追加申請が料金ゼロ!
月額11,000円
お得な年間サポートパック
このページで分かること
制度の背景と目的
機体の登録制度が発足した背景は、皇居の近くを夜間ドローンが飛んだときに機体の所有者を特定できなかったという事件です。

機体所有者が特定できず安全上必要な措置がとれない問題もさることながら、特に事故発生時などでは無人航空機の所有者を把握することは極めて重要なことです。
今後、無人航空機の利活用拡大を目指す国としては「安全・安心の 確保」は喫緊の課題であるとして導入された制度です。
2022年6月20日以降、100g以上200g未満のドローンも飛行許可申請が必要になりましたが登録記号は飛行許可申請にも直接関係してくるので重要なものになっています。
機体登録しなければ飛ばせない
飛行許可申請時には機体登録後に発行される最新の登録記号を入力しなければいけません。
これまでの飛行許可申請では製造番号当局の番号だけで許可申請できましたが今後登録記号というものも入力する必要があります。
飛行許可申請手続きの流れも、この機体登録をした後でないと許可申請に進めない順序となっています。
つまりこの登録記号がないものについては許可申請のシステム上も受け付けてもらえなくなっています。
そして、これもポイントですが飛行許可を受けて飛ばす際には「登録記号が表示されたドローン」で飛ばさなければならないルールとなっています。

具体的にはGUナンバーと呼ばれるGUから始まる登録記号を機体に表示(記載・装着)するものです。
登録記号は製造番号と同じ重要な位置づけとなったわけです。
リモートIⅮで飛行中に所有者特定
この制度と切っても切り離せない新たな義務がもう一つ発足しました。
リモートIⅮ搭載義務です。
前述したように、機体登録後に発行されるドローンを識別するための記号(登録記号)を機体に表示しなければなりませんが、更に機体には「リモートIⅮ機能」を備えた状態でなければ飛ばしてはいけないというものです。
「リモートIⅮ」とは、機体登録時に申請した登録情報を機体から電波で発信するICチップのようなものです。
車のナンバープレートの電波バージョンと理解すればいいでしょう。

形態としてはチップのようなものの外付けか、機体内臓の二つです。
2022年6月20日から全てのドローンに搭載必要になりました。
このリモートIⅮ機能によって、飛んでいるドローンが発信する電波を受信し機体の所有者を特定するという機体管理の仕組みです。
今まさに目のまえで飛んでいる機体が誰のドローンなのかを、警察官などの当局が受信機によって確認し機体の所有者を現場で突き止めるという、ドローン機体登録制度の主眼とも言えるのがこのリモートIⅮ機能です。
今後は標準装備化
既存の機体外にリモートIⅮを装着するか、もともと機体メーカーの方で機体の中に埋め込まれているものかのどちらかの機能を備えなければいけません。
このチップは高額(2~3万円)なものとなるため所有者はリモート ID搭載の機体に買い替えない限り新たな負担を強いられることになります。

外付けタイプは高額な上に、一台づつ購入しなければならないのでこれを単体で購入する人は少ないのではないでしょうか。
6月19日までに機体登録を済ませたドローンについてはリモートIDを搭載する必要がないという経過措置がとられたので、6月は国交省への駆け込み登録が殺到しました。
このリモート IDは最も軽いものでも20~30gの重さになり100g から199g の小さなドローンについては飛行性能に影響が出やすくなります。
150g に30gのリモート IDが つくとその負荷の影響で飛ばす時間にも影響が出てきます
そしてこのことは飛行許可手続きにも影響を及ぼすものとなっていきます。
機体メーカーのリモートID搭載型のドローンは新機種として扱われますが、リモートIDを機体の外部に別途装着した場合は「機体の改造」とみなされ改めて飛行許可申請が必要となります。
この点も一般の方には非常に判りにくい部分なので、外付けを選んだ方にとってはしばらくは様々な手間が生じることが予想されます。
いずれにせよ、これから製造されるドローンについてはリモートIDが標準装備されるでしょうから、車と同様に機体管理制度(持ち主特定制度)が安定して運用されていくことでしょう。
機体登録の有効期間は3年
機体登録の有効期間は3年間となっています。
事前登録として2022年6月19日までに登録された機体は、リモートIDがつけられていなくても機体が壊れない限り永遠に搭載しなくても良い経過措置が設けられました。
但し 6月20日以降にドローンが壊れてしまって改めて登録し直す場合にはその時点からリモート IDをつけなくてはいけません。
機体登録制度はドローン登録システム(DRS)によって登録申請することになります。
紙申込にも対応していますがやはり中心はこのオンラインシステムで、英語でも使用でき海外でも外国人でも使用して登録できるシステムになっています。
パソコンとスマートフォンを使うシステムで一度の申請で最大20台までの登録が可能です。
この制度はドローン手続関係では初めて「有料」でスタートしました。具体的な料金は申請方法で変わっています。
そのあたりも含めての具体的な登録方法はこのページで紹介しています。
機体登録できないドローンとは
ドローンの中には機体登録ができないドローンというものもあります。
- 製造者側が安全に懸念があるとしてリコールしているドローン
- 事故が多発していることが明らかなドローン
- 不要な突起物が付いて安全を損なうようなドローン
- 遠隔操作や自動操縦の制御が困難であるドローン
- 既に登録されている機体とメーカー名と機体名・製造番号が同じもの
等々、国交省が指定したものは登録できません。
現在指定されている危険な機体はありませんが、今後車と同じようにリコール対象のものが出てくる可能性があります。
また実際に起きた事例として、プロペラ機の後が尖ったアクセサリーのようなものを付けていたために登録できなかったケースも既にあります。
4,については、そもそも飛ばすのが困難なドローンを登録しても業務で使う意味は無いので登録できない対象となっています。
そして、重複登録できないということです。
これができてしまうと制度導入の最大目的である「所有者の特定」ができなくなり制度の趣旨に反するということで、同一のものの登録はできないことになっています。
登録記号は自分の手で装着する義務
機体の登録手続きを完了すると登録記号というのが発行されます。
この番号は自動車のナンバープレートみたいに登録番号を自分で希望することはできず当局で決められた番号が与えられます。
そしてこの記号はドローンの機体の容易に取り外しが出来ない部分に外部から確認しやすい箇所にテープ貼付かマジック記載などで前面に表示しなければいけません。
自動車と違って自分で表示しなければなりません。
発行される登録記号の文字はドローンの大きさによって文字のサイズが決められています。
機体の横とかにテプラで貼り付けたりするのが一般的ですがマジックだと消せなくなって困るのでテプラがお勧めです。
機体登録の削除、変更
修理などで変わった場合は機体登録も削除(自動車で言う抹消)をしなければなりません。
そしてその後に新しい機体登録を新規で行わなければなりません。
その新規に登録した機体の登録記号を用いてDIPSで「飛行許可の変更申請」を行うことになります。
機体の番号が変わったり新しく機体が増えた場合は機体の登録の削除や新規登録が必要になり、同時に飛行許可申請の方は機体で追加の変更申請が必要になります。

修理で製造番号変わったら注意
製造番号に関してはDJIのドローンなどでよくあるのですが修理等で製造番号が変わった場合は(修理等で番号は変わります)、それが同じドローンであっても見た目も同じであっても更にきれいになって外側だけ変わっただけでも製造番号が変わってることがあります。
こちらも知らない方が多いので注意しましょう。
このケースでは、製造番号が変わって戻されてきたことを気づかずに(知らずに)飛ばしてしまい無許可飛行で検挙された事例が実際にあります。
DJI のドローンは特に製造番号変わるという傾向が強いのでこの可能性を考慮する必要があります。
修理を出す際も例えばカメラだけ修理に出すよりも新しい機体に取り替えた方が安い場合もあるので、そこはよく考えて判断しましょう。
インターネットの保険ではDJIの機体の場合保険加入するときに製造番号が必要となります。
製造番号というのは機体によって確認する場所が異なっています。
人によってはどこにそんな番号あるのかわからないとかという方もいますがネットで調べれば「製造番号がどこにあるのかが判るサイト」というものも出ていますのでご活用ください。
システムの改善の期待
最後にこの機体登録制度の本来の趣旨とは離れて、一点期待できることがあります。
今後のドローン関連システムの改善です。
DIPSとかFISSといった現行システムは現在のところ手数料無料で使えていますが、逆にこのためにシステムの改修やの審査官の教育などに要する時間や費用が確保できないという事情がありました。
そのため非常に使い勝手の悪いシステム状態が長期にわたって解決されず、その結果使用者に不便を強いる状況が続いています。
この打開策としてこの機体登録の制度では手数料を徴収することになりました。
本人の確認資料提示等の方法によって色々違ってはきますが、基本的には有料のシステムです。
近い将来にはこれを財源としてこの機体登録のシステム「DRS」と飛行情報の共有登録システム「FISS」そして許可申請の「DIPS」。
この3つのシステムが統合され利用者にとっての利便性は格段にあがることになるでしょう。
【県別】場所別の規制と手続き
飛ばせる場所の確認方法と規制
国立公園で飛ばす規制と手続き
山で飛ばす:国有林入林届
観光地で飛ばす:観光協会一覧
海で飛ばす規制と手続き
みなとで飛ばす手続き
文化財の空撮:注意と手続き
ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】
四十七都道府県別ドローン規制と飛行許可申請手続き
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。